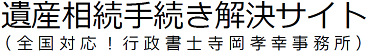行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
行政書士のプロフィールはこちら
代表相続人(相続人代表者)とは、
特に、銀行の相続手続きで、相続人全員を代表して、
亡くなった人の預貯金の全額を受け取る人のことを言います。
代表相続人(相続人代表者)は、
亡くなった人の預貯金を受け取る人のことを言いますので、
代表受取人(だいひょううけとりにん)と呼ぶこともあります。
銀行の相続では、亡くなった人が銀行口座を持っていれば、
その口座が凍結された後、
相続手続きを行い、口座凍結の解除をしなければなりません。
そして、口座凍結の解除がされれば、
通常、どこの銀行でも、代表相続人1名に、
亡くなった人の預貯金の全額が振り込まれる流れになっているのです。
そのため、銀行の相続手続きを進める時には、
まず、銀行から預貯金の全額を受け取る代表相続人を、
1名決めておく必要があります。
もし、亡くなった人の口座の預貯金を、
相続人全員で均等に分けることが決まっていたとしても、
代表受取人とも言える代表相続人を決める必要があるのです。
また、 相続人の内、数人が預貯金を受け取り、
他の数人が預貯金の代わりに、
不動産などを受け取る場合でも同じです。
いずれの場合でも、銀行から、
亡くなった人の預貯金を受け取る時には、
相続人全員で話し合って、代表相続人1名を決める必要があります。
なぜなら、銀行の相続では、手続き完了時に、
銀行から各相続人に対して支払われるわけではなく、
代表相続人1名に、預貯金の全額が支払われる流れになっているからです。
もし、銀行の相続手続きでお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行預金の相続手続き (払戻し・清算手続き) に困っていませんか?
次に、代表相続人(相続人代表者)が、
亡くなった人の銀行預貯金の全額を受け取った後、
代表相続人として行うべきことについてです。
もし、遺産分割協議によって、
他の相続人も、いくらか現金を受け取ることが決まっていれば、
その通りに、代表相続人が、各相続人に配分することになります。
相続人同士が遠くてなかなか会えないような場合には、
できるだけ速やかに、各相続人の銀行口座に、
代表相続人から振り込むようにします。
やはり、現金の手渡しよりも、
入出金の記録が残る振り込みの方が、
後々面倒なことになることがないので良いでしょう。
また、銀行の相続手続きをする前に、
相続手続きに必要な戸籍の謄本類をすべてそろえることと、
遺産分割協議書についても、作成しておいた方が良いです。
なぜなら、銀行から代表相続人に全額が振り込まれ、
その後で、代表相続人から、各相続人に振り込む流れになるため、
税務署などに、贈与とみなされる可能性があるからです。
そのため、通常の贈与ではなく、相続財産であることを示すため、
相続した現金の流れが、誰が見てもはっきりとわかるように、
遺産分割協議書を作成しておいた方が良いということです。
ただ、代表相続人(相続人代表者)から、他の相続人に対して、
配分する金額が110万円以下でしたら、
贈与税の基礎控除内でおさまりますので、問題になることは無いでしょう。
つまり、代表相続人(相続人代表者)から、
各相続人に支払う金額が、100万なら、
贈与税の基礎控除110万以下のため、贈与税は必要ありません。
年間110万円までの贈与には、
贈与税がかからないことになっているからです。
もし、銀行の相続で、
遺産分割協議書の作成の仕方がよくわからない場合には、
遺産分割協議書の書き方のページが参考になります。
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。