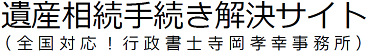行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:相続関連手続き全般。
経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行っています。
行政書士のプロフィールはこちら
亡くなった人のゆうちょ銀行口座に少額の貯金しかない場合、
通常の手続きとは違った簡易的な手続きが可能です。
ゆうちょ銀行では、
亡くなった人の貯金額が100万円以下を少額扱いとしています。
ただし、通常貯金と定期貯金など、
亡くなった人の口座にある貯金額が、
100万円以下であることが必要です。
逆に言えば、亡くなった人のゆうちょ銀行にある貯金額が、
100万円を超えていれば、少額とは言えません。
そのため、100万円を1円でも超えていれば、
通常の相続手続きが必要になります。
もし、銀行の相続手続きでお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行預金の相続手続き (払戻し・清算手続き) に困っていませんか?
では、ゆうちょ銀行で少額と判断された場合、
どういった相続手続きの流れになるのかについてです。
まず、亡くなった人の貯金が100万円以下と考えられる場合には、
ゆうちょ銀行窓口のある郵便局に行きます。
そして、郵便局の局員が、
亡くなった人の口座の正確な残高を調べますので、
少額かどうかの判断は窓口局員に任せます。
亡くなった人のゆうちょ口座の貯金が少額と判断された場合、
相続手続きの流れとしては、大きく分けて2通りあります。
1つは、相続確認表という3枚つづりの用紙に、
代表相続人1人がすべてを記入して手続きが終わる流れです。
もう1つは、相続確認表に記入した上で、
郵便局の貯金事務センターに手続き書類が送られる流れです。
いずれの場合でも、郵便局の窓口局員の指示に従がって手続きを進めます。
なぜなら、亡くなった人の口座の状況によって、
細かく流れが決まっているため、
その時の局員の判断に従うしかないからです。
ちなみに、郵便局の貯金事務センターに、
手続き書類が送られる場合には、
Aー5(支払請求書)の用紙も必要になります。
ただ、Aー5(支払請求書)の用紙には、
代表相続人がすべて記入できますので、
他の相続人の署名などは必要ありません。
また、最初に記入が必要になる相続確認表も、
代表相続人がすべて記入できるものです。
そのため、亡くなった人のゆうちょ口座の金額が100万円以下の場合には、
代表相続人1人で手続きが完了できるということです。
つまり、他の相続人の署名や実印の押印無しで、
亡くなった人の貯金の全額を引き出すことが可能ということになります。
また、貯金額が100万円以下の場合には、
他の相続人の印鑑証明書も必要ありません。
ただ、相続手続きに必要な戸籍の謄本類については、
貯金額が10万円以下なら必要ありませんが、
10万円を超えていれば必要になります。
つまり、貯金額が100万円~10万円の間なら、
少なくとも、亡くなった人と代表相続人の相続関係を、
証明できる範囲の戸籍の謄本類が必要ということです。
もし、相続手続きに必要な戸籍の謄本類でお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行の相続手続きに必要な戸籍で困っていませんか?
なお、ゆうちょ銀行の預貯金が少額(100万円以下)の場合は、
ゆうちょ銀行の相続確認表と代表相続人が重要になります。
逆に、ゆうちょ銀行の預貯金が100万円以上の場合は、
必要書類と手続きの流れに大きな違いがありますので、
「ゆうちょ銀行の相続の必要書類」、「ゆうちょ銀行の相続手続き」を参照ください。
また、亡くなった人の銀行預金が少額かどうかは各銀行ごとに違うため、
少額ではない銀行預金(通常50万~100万円以上)の相続の仕方については、
「銀行預金を相続する方法」で具体的な手順を解説しています。
【関連記事】
もし、銀行の相続手続きでお困りの方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行預金の相続手続き (払戻し・清算手続き) に困っていませんか?
【次の関連性の高いページもよく読まれています。】